酒井先生に聞く~相手に伝わるビジネス文書作成のコツとは~

2024/11/18
今回は、新入社員だけでなく、中堅社員や管理職対象にも実施しているという「ビジネス文書研修」について、マナー講師の酒井もえ先生に伺います。
酒井 もえ 先生 プロフィール:
大手通信企業コールセンター部門、メーカーのカスタマーサポート業務に10年以上従事。その後、声だけが頼りの電話応対の難しさを感じ、声や言葉の表現力を習得するためにアナウンススクールで学びプロの司会者として独立。
司会で様々な企業と関わり、お客様と良い関係を築くにはマナーが不可欠であることを感じ、講師を目指す。
人を気遣う気持ちは言葉や表情などで表現しないと伝わらない。自分がどのような印象を他者に与えているのかを考え、気づく力を養い、行動変容する指導を行っている。
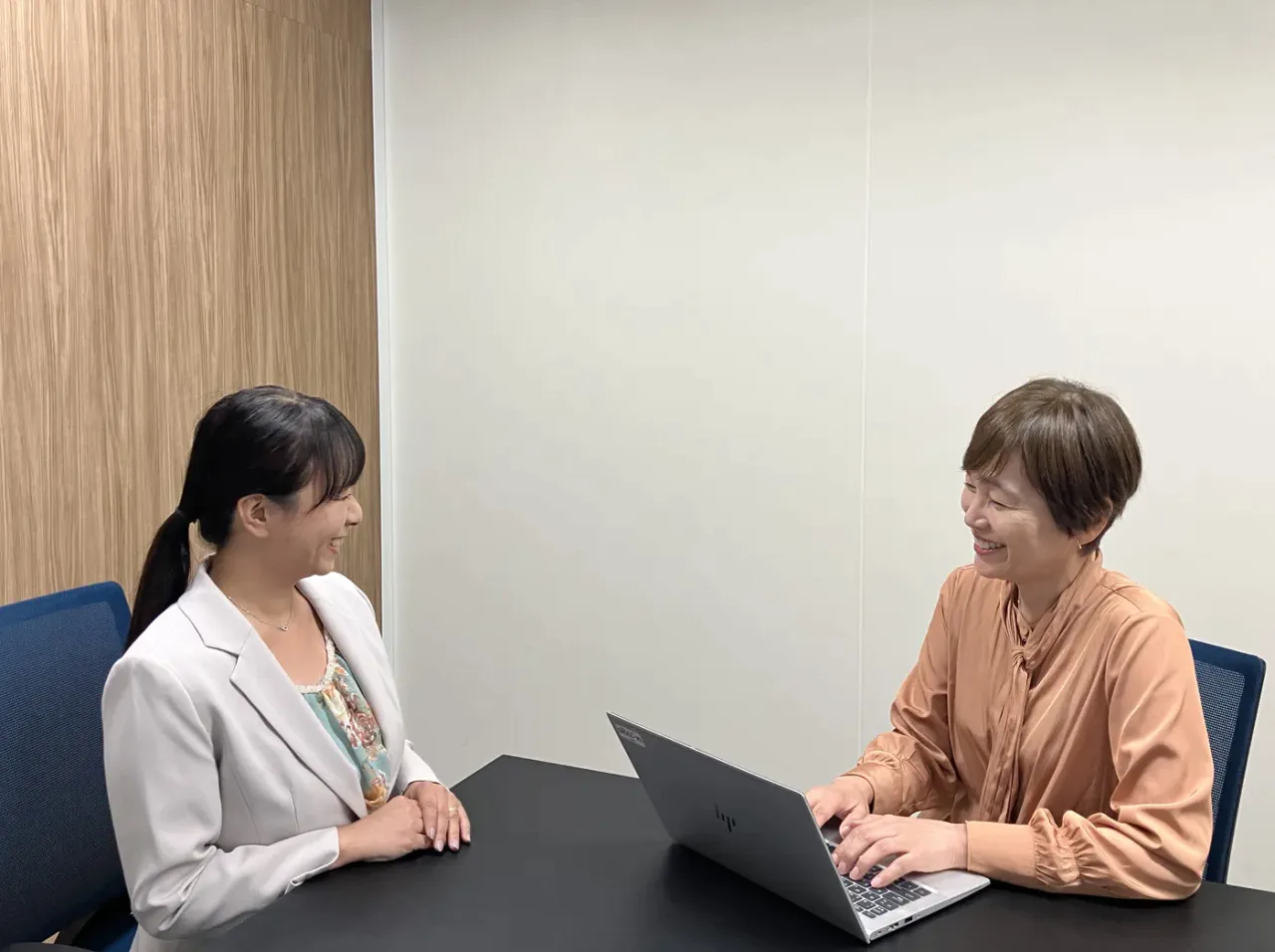
聞き手|アビリティーセンター企業研修グループ 田中恵子(元高知放送アナウンサー)
中堅社員や管理職にも必要とされているビジネス文書研修
-ビジネス文書研修というと、新入社員研修の中で実施するものというイメージですが、中堅社員や管理職を対象としたご依頼もあるようですね。
酒井:そうなんです。最近は若手社員に並んで、中堅や管理職の方への研修の需要が増えています。また、文書を作成することが多いオフィス勤務の方だけでなく、営業の方や現場の管理職など受講される方の幅が広がっていますね。
-必要とされる背景には何があるんでしょうか?
酒井:ビジネス文書には基本的なマナーがあります。そのマナーを新入社員の方には学んでいただきますが、実務で経験が浅い新入社員の時よりも、実務で経験を積んできた方の方が、文書作成時に迷いや疑問が出てくるものです。というのも、ビジネス文書はその会社の社風が現れたり、業務の礎を築いてきた先輩方の文書を受け継いでいたりしますが、時代とともに「この表現は古いかも?くどいかも?」という疑問がわいてくる。でも、それを崩していいものかわからない。そこで改めて、正しい文書作成のスキルを身につけたいという需要が生まれていると思います。
-確かに、紙で保管していた時代から、ビジネス文書の形も変わってきていますから、変化に対応するためにも、改めて基本を学ぶことは大切ですね。
講義だけではない、対話を意識した研修スタイル
-ただ、大事な研修の一つだと思うのですが、どうしても、企業研修の中では地味と言いますか、受講者からするとつまらないと思われている印象です・・・酒井先生はどんな工夫をされていますか?
酒井:ビジネス文書研修だけでなく、私は登壇する時にこだわりがありまして説明だけが長くならないようにしています。要点を話して、個人ワークをしてもらい、グループディスカッションで意見交換をすると、他の人の意見を聴くことができて、学びに繋がります。受け身にならず、進んで参加できる環境を作れるよう、受講者との対話にも気を配っています。
-なるほど。「ルールはこうです」「この書き方は正解です。不正解です」だけではなく、対話をしながらの研修なんですね。
酒井:そうなんです。作成した文書を見せ合って、他の人はどう書いているのかを知る。同じなら共感していただけますし、違えば、「そこもらおう!」となったりして、その気づきが学びになります。また、あえて間違った文書を見てもらって間違い探しをしてもらうこともありますよ。考えすぎてあれもこれも直してしまうのが面白くて盛り上がります。
伝わる文章を書くためのポイント、上達のコツ
-ビジネス文書の基本的なマナーに加え、伝わる文章を書くのが難しいという悩みもありますよね。
酒井:そうですね。伝わる文章を書くポイントは大きく分けて3つです。1つ目は「正確に書くこと」。内容が間違っていると、会社の信頼に影響します。2つ目は「分かりやすいこと」。内容が明確で簡潔に書くことと、短くわかりやすい表現をすることです。3つ目は「読み手を意識すること」です。私はこれがとても大事だと思っています。相手の立場や相手がどのような情報が欲しいかを考慮することで、伝えるではなく、伝わる文章になると思います。
-上達するにはどうしたらいいでしょうか?
酒井:やはり読み手の気持ちになって作成することですね。短くて分かりやすい文章、具体的にいうと、余計な説明や不要な言葉を省くことで、読み手に負担をかけない文章を作成できます。また、作成後にしっかりと見直し、他者の意見をもらうことも有効です。書いた文章を声に出して読んでみるというのもおすすめですよ。音読すると繋がりがおかしいなとか、一文が長すぎることに気づくことができるんです。
-それは私も元アナウンサーとしてよくわかります。上手な人が書いた原稿は読みやすいから、かまないですよね!
ビジネスシーンでも利用が進むLINEの留意点
-ところで最近は、いわゆる社外文書・社内文書に加えて、電子メールやLINEでのやりとりについてご相談を受けることが増えていますよね。
酒井:はい。ご依頼があれば、電子メールはもちろん、ビジネスチャットツールやLINEでのやりとりについてもお伝えしています。こういったツールは、気軽にやりとりできますが、省略が多くなってしまうことが問題になっていると感じます。
-省略が多いと言いますと?
酒井:例えば、複数人のチャットで「わかりました」だけだと、誰に向けてのリプライで、何がわかったのかが伝わらない。「〇〇部長、〇〇の件、承知しました」とする、「また連絡します」ではなくて「いつまでに連絡します」とすることが必要です。こういった大切な情報を省略してしまうと、「言ったつもりだった」「そういう意味だと思っていなかった」というトラブルの元になります。便利になっているからこそ、大切な情報は省略しないことが大切だと感じております。
-ビジネス文書も、LINEなどのツールも、大事にすることは本来のコミュニケーションと同じなんですね。
酒井:おっしゃる通りです。自分がどう伝えたかではなく、相手がどう受け止めたか、相手を意識することが大切ですね。
-どうもありがとうございました。
酒井先生の研修にご興味をお持ちいただきましたら、是非営業担当者、もしくはお問い合わせフォームからご連絡をいただけたら幸いです。
 アビリティーセンター企業研修
アビリティーセンター企業研修